
惛枾懴恔恌抐偼堦斒懴恔恌抐傛傝丄
寶暔偺奺晹埵偺嫮搙傪嬶懱揑偵峫椂偟偰寶暔偺懴椡傪恌抐偡傞曽朄偱偡丅
偍傕偵丄摦揑懴恔恌抐傗堦斒懴恔恌抐偱懴恔夵廋偑昁梫偲敾抐偝傟偨応崌偺
曗嫮愝寁偍傛傃曗嫮屻偺懴椡専徹傪偡傞偨傔偺堦偮偺庤抜偱偡丅
 惛枾懴恔恌抐偲偼丠
惛枾懴恔恌抐偲偼丠  恌抐偐傜傢偐傞偙偲
恌抐偐傜傢偐傞偙偲  曬崘彂僒儞僾儖
曬崘彂僒儞僾儖
亂 惛枾懴恔恌抐偲偼丠 亃
惛枾懴恔恌抐偼摦揑懴恔恌抐傗堦斒懴恔恌抐偱懴恔夵廋偑昁梫偲偝傟偨応崌丄懴椡晄懌偺暻偺嫮搙傪偳傟偔傜偄偵偟偨傜椙偄偐傪婛懚寶暔偺忬懺傪峫椂偟偰寁嶼偱専徹偡傞偨傔偺曽朄偱偡丅彯丄怴懴恔婎弨偵傛傞専徹偼峔憿寁嶼傪峴偄敾抐偟傑偡丅
亂 惛枾懴恔恌抐偐傜傢偐傞偙偲 亃
寶暔偑曐桳偡傞懴椡偲昁梫懴椡乮抧恔椡傪峫椂乯傪斾妑偟偰偦偺寶暔偑埨慡偐偳偆偐傪寁嶼偵傛傝恌抐偟傑偡丅
侾乯昁梫懴椡偺嶼掕
丂寶抸婎弨朄巤峴椷偵弨偠偰嶼弌偟傑偡丅壓婰抧恔椡俻i傪昁梫懴椡俻倰偲偟傑偡丅
乮抧恔椡乯
俻i亖俠i亊儼倂i
戞88忦丂寶抸暔偺抧忋晹暘偺抧恔椡偵偮偄偰偼丄摉奩寶暔偺奺晹暘偺崅偝偵墳偠丄摉奩崅偝偺晹暘偑巟偊傞晹暘偵嶌梡偡傞慡懱偺抧恔椡偲偟偰寁嶼偡傞傕偺偲偟丄偦偺悢抣偼摉奩晹暘偺屌掕壸廳偲愊嵹壸廳偲偺榓乮戞86忦戞2崁偨偩偟彂偒偺婯掕偵傛偭偰摿掕峴惌挕偑巜掕偡傞懡愥嬫堟偵偍偄偰偼丄峏偵愊愥壸廳傪壛偊傞傕偺偲偡傞丅乯偵摉奩崅偝偵偍偗傞抧恔憌偣傫抐椡學悢傪忔偠偰寁嶼偟側偗傟偽側傜側偄丅偙偺応崌偵偍偄偰丄抧恔憌偣傫抐椡學悢偼師偺幃偵傛偭偰寁嶼偡傞傕偺偲偡傞丅
俠i亖倅俼倲俙倝俠倧
偙偺幃偵偍偄偰丄俠i丄倅丄俼t丄俙i偍傛傃俠o偼丄偦傟偧傟師偺悢抣傪昞偡傕偺偲偡傞丅
俠i丗寶抸暔偺抧忋晹暘偺堦掕偺崅偝偵偍偗傞抧恔憌偣傫抐椡學悢
倅 丗偦偺抧曽偵偍偗傞夁嫀偺抧恔偺婰榐偵婎偯偔恔奞偺掱搙媦傃抧恔妶摦偺忬嫷偦偺懠抧恔偺惈忬偵墳偠偰1.0偐傜0.7傑偱偺斖埻撪偵偍偄偰崙搚岎捠戝恇偑掕傔傞抣丅
俼t丗寶抸暔偺怳摦摿惈傪昞偡傕偺偲偟偰丄寶抸暔偺抏惈堟偵偍偗傞屌桳廃婜媦傃抧斦偺庬椶偵墳偠偰崙搚岎捠戝恇偑掕傔傞曽朄偵傛傝嶼弌偟偨悢抣
俙i丗寶抸暔偺怳摦摿惈偵墳偠偰抧恔憌偣傫抐椡學悢偺寶抸暔偺崅偝曽岦偺暘晍傪昞偡傕偺偲偟偰崙搚岎捠戝恇偑掕傔傞曽朄偵傛傝嶼弌偟偨悢抣
俠o丗昗弨偣傫抐椡學悢偼丄0.2埲忋偲偟側偗傟偽側傜偄丅偨偩偟丄抧斦偑挊偟偔擃庛側嬫堟偲偟偰摿掕峴惌挕偑崙搚岎捠戝恇偺掕傔傞婎弨偵婎偯偄偰婯懃偱巜掕偡傞嬫堟撪偵偍偗傞栘憿偺寶抸暔乮戞46忦2崁戞1崋偵宖偘傞婎弨偵揔崌偡傞傕偺傪彍偔丅乯偵偁偭偰偼丄0.3埲忋偲偟側偗傟偽側傜側偄丅
昁梫懴椡俻r傪嶼弌偡傞嵺偺廳検偼丄廧戭娙堈廳検昞偲偟偰壓昞傪嵦梡偟丄堦斒懴恔恌抐乽彴柺愊偁偨傝偺昁梫懴椡乮倠N/噓乯乿偵奺奒偺彴柺愊傪忔偠偰媮傔傑偡丅
俀乯曐桳偡傞懴椡偺嶼掕
丂曐桳偡傞懴椡乮俻倓乯偼壓幃偵傛傝嶼掕偟傑偡丅
丂俻倓亖乮俻wn亄俻ww乯亊俥s亊俥e
丂丂俻d丂丂丂丗曐桳偡傞懴椡
丂丂俻wn丂丂丗柍奐岥暻偺懴椡
丂丂俻ww丂丂丗桳奐岥暻偺懴椡
丂丂俥s丂丂丂丗崉惈棪偵傛傞掅尭學悢
丂丂俥e丂丂丂丗曃怱棪偲彴巇條偵傛傞掅尭學悢
俁乯寶暔懴椡偺昡揰
丂奺奒丄奺曽岦乮倃丄倄乯偵偮偄偰丄曐桳偡傞懴椡乮俻d乯傪昁梫懴椡乮俻r乯偱彍偟偨抣傪嶼弌偟懴椡昡揰偲偡傞丅
丂懴椡偺昡亖俻d/俻r
係乯奺晹偺専摙丂丂壓婰偺崁栚傪挷傋偰曬崘偟傑偡丅
丂(1)抧斦
丂(2)婎慴
丂(3)悈暯峔柺偺懝彎
丂(4)拰偺愜懝
丂(5)墶壦嵽愙崌晹偺奜傟
丂(6)壆崻晿偒嵽偺棊壓偺壜擻惈
俆乯忋晹峔憿偺懴椡偺昡壙
丂壓昞偵傛傝敾抐偟傑偡丅
| 忋晹峔憿昡揰 | 敾掕 |
| 1.5埲忋 | 搢夡偟側偄 |
| 1.0埲忋1.5枹枮 | 堦墳搢夡偟側偄 |
| 0.7埲忋1.0枹枮 | 搢夡偡傞壜擻惈偑偁傞 |
| 0.7枹枮 | 搢夡偡傞壜擻惈偑崅偄 |
亂 惛枾懴恔恌抐丒曬崘彂僒儞僾儖 亃
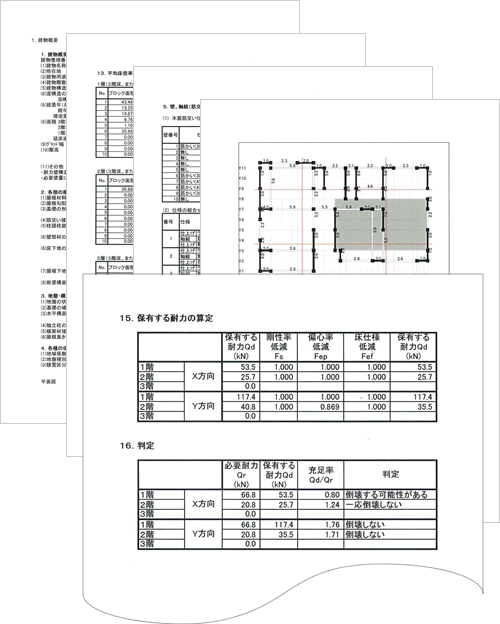




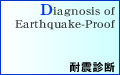

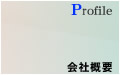

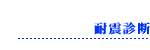
 惛枾懴恔恌抐
惛枾懴恔恌抐